超小型自動車3人乗りモデル最新情報
超小型自動車3人乗りの法的区分と特徴
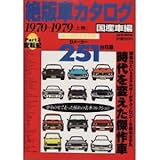
絶版車カタログ 国産車編 Part2 超A級完全保存版: 夢をのせて走った憧れの名車コレクション (EICHI MOOK)
超小型自動車の3人乗りモデルは、従来の自動車とは異なる独特な法的位置づけを持っています。道路交通法では「普通自動車」として扱われるため、普通自動車免許が必要でヘルメット着用義務がありません。一方、道路運送車両法では「側車付軽二輪」に分類されるため、車検や車庫証明が不要という特徴があります。
この「半分クルマ、半分バイク」という不思議な位置づけにより、運転方法はクルマと同様でありながら、維持費はバイク並みという両者のメリットを享受できます。乗車定員は最大3名で、運転席に1名、後部座席に2名が乗車可能です。
国土交通省の定義では、超小型モビリティは「ミニカー(第一種原動機付自転車)」「超小型モビリティ(型式指定車)」「超小型モビリティ(認定車)」の3つに分類されており、現在市場に出回っているのは主に型式指定車となっています。
超小型自動車3人乗りの価格帯と主要モデル
2024年から2025年にかけて、超小型自動車の3人乗りモデルが続々と登場しています。価格帯は59万円から104万円と幅広く、用途や予算に応じて選択できます。
主要モデルの価格比較
- VIVEL TRIKE:59万円〜62万円
- FAVICLE:64万9000円
- eNEO:88万円〜
- ジンマ:77万円〜104万5000円
最も注目されているのは、バブル社の「VIVEL TRIKE(ビベルトライク)」で、62万円という価格でありながら最大3人乗車が可能な広い後部座席とトランクを備えています。全長2250mm×全幅1020mm×全高1620-1650mmのコンパクトなボディながら、1500Wの高出力バッテリーを搭載し、最高時速45-60km/hで走行できます。
アントレックス社の「FAVICLE(ファビクル)」は64万9000円で、2000Wのパワフルなモーターを搭載し、坂道でも快適に走行できる性能を持っています。
超小型自動車3人乗りの性能と実用性
超小型自動車の3人乗りモデルは、コンパクトなサイズながら実用性の高い設計が特徴です。多くのモデルが3輪構造を採用しており、前輪2つ、後輪1つの配置により高い安定性を実現しています。
主要性能比較表
| モデル | 最高出力 | 最高速度 | 航続距離 | 充電方式 |
|---|---|---|---|---|
| VIVEL TRIKE | 1500W | 45-60km/h | 未公表 | AC100V |
| FAVICLE | 2000W | 未公表 | 未公表 | 家庭用コンセント |
| eNEO NEO-ONE | 未公表 | 未公表 | 未公表 | 未公表 |
| ジンマ ハイエンド | 3000W | 未公表 | 100-120km | AC100V/200V |
ジンマのハイエンドモデルは3000Wの最高出力を誇り、航続距離も100-120kmと長距離走行に対応しています。充電方式もAC100VとAC200Vの両方に対応し、充電スポットでの利用も可能です。
実用面では、後部座席を荷物スペースとして活用できる設計が多く、1人での使用時には大容量の荷物を積載できます。また、別売りのレインカバーを装着することで、雨風を防ぐことも可能です。
超小型自動車3人乗りの運転体験と安全性
超小型自動車の3人乗りモデルは、従来の自動車とは異なる独特な運転体験を提供します。トヨタが開発した「i-ROAD」の後継モデル「リーン3」では、3輪で車体の安定性を確保しつつ、旋回時はバイクのように倒れ込む(リーン)機能を備えており、オートバイでコーナーを駆け抜けるような喜びを味わえます。
安全性の面では、多くのモデルがディスクブレーキシステムを採用しており、4輪車と同等の制動力を確保しています。3輪構造による高い安定性により、舗装路はもちろん多少の悪路でも安全に走行できます。
操作系はバイクと同様のハンドルバータイプが一般的ですが、普通自動車免許で運転でき、ヘルメットの装着も不要です。シートベルトの着用義務もないため、気軽に乗り降りできる利便性があります。
実際の乗車体験では、174cmの成人男性が後席に座る場合、運転席を前方にスライドさせる必要があるものの、頭上と肩まわりには十分な余裕があり、3人乗車でも短時間であれば快適に過ごせるという評価があります。
超小型自動車3人乗りの将来性と市場動向
超小型自動車の3人乗りモデルは、日本の地方部における公共交通の脆弱化を補完する新たなモビリティとして期待されています。バスやタクシーといった従来の公共交通機関の代替手段として、地域の活性化にも貢献する可能性があります。
環境面では、超小型モビリティのエネルギー消費効率は走行距離あたりガソリン車の6分の1程度で、大幅な環境負荷削減が期待されています。100%電気駆動により排ガスゼロを実現し、財布にも環境にも優しいエコな移動手段として注目されています。
市場動向としては、2024年から2025年にかけて複数のメーカーが新モデルを投入しており、競争が激化しています。価格帯も59万円から104万円と幅広く設定され、消費者の選択肢が大幅に増加しています。
用途も多様化しており、通勤や買い物といった日常使いから、観光やレジャー、配達業務まで幅広いシーンでの活用が想定されています。特に家族連れからの注目度が高く、子供の送迎や家族でのお出かけに適した移動手段として評価されています。
今後は、サイドドアの設定や航続距離の延長、充電インフラの整備などにより、さらなる実用性の向上が期待されています。また、自動運転技術の導入により、高齢者や運転に不安を感じる方でも安心して利用できる移動手段として発展する可能性もあります。
超小型自動車の3人乗りモデルは、従来の自動車とバイクの中間に位置する新しいカテゴリーとして、日本の移動手段に革新をもたらす存在となりそうです。環境性能と経済性を両立し、都市部の狭い道路でも快適に走行できる特性により、今後ますます注目を集めることが予想されます。
絶版車カタログ 国産車編 Part5 超A級完全保存版 (EICHI MOOK)


